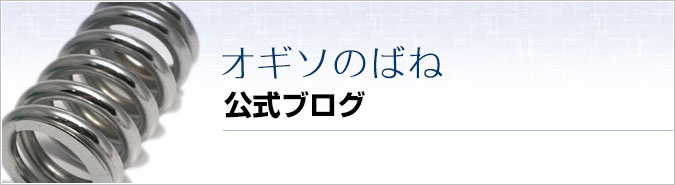
進化はしないが、変化はできる。できる男になってやる。
完全スルー
2015.12.05
カテゴリ : こども/カミさん/ファミリー
この春、都内の大学へ娘が進学して早くも年末になります。
親の心配をよそに、本人は都会での学生生活を大いに満喫しているようです。
とはいえ、人が多い大都会では何が起こってもおかしくないこのご時世。
何かにつけ、こちらからメールやLINEを送ったりして様子を探っているのですが、
返事がこない、こない、・・・・・・。
既読スルーどころか、既読すらしないようで。
完全スルー?
1日、2日遅れの返事は当たり前!になってきた今日この頃。
“便りがないのは、いい知らせ” と家族で話しています。
とは言え、やっぱり心配ですけどね。
好きな女(ひと)
2015.11.22
カテゴリ : 日記
最近のTVを見ていて、私が気になる女性は何人かいる。
例えば、土屋太鳳(つちやたお)だったり、波瑠(はる)だったり。
ん? NHK率が高いのは歳をとってきたせいか?
でも、今の一番は、
松岡 茉優(まつおか まゆ)でしょ!社長!!
で、今出てるドラマも楽しみの一つでもあるのですが。
ウチのカミさん、娘いわく
「出たがり感がすごい」「うるさい」
「ちょっとないわ~」
だと。
まあ、男と女の好みは違うわな。(あと、ひがみもあるのでしょうが)
そんな折、TVを見ていたカミさんが、
「ほら、ほら、早く!あなたの好きな女(ひと)が出てるよ!」
と、別の部屋にいた私をわざわざ呼ぶので、(大きい声で)
『え?マジで!』
少し喰い気味に勢い込んでTVに駆け寄ると、そこには!
♪ まも~りたい、あいするかぞ~くを~~ ♪
ふざけんなよ!吉田じゃねーかっ!!
よりにもよって。おい!
誰が、霊長類最強女子なんかっ!
なんか前より可愛くなってるけども。
「だって、あなた強い女(ひと)が好きだって言ってたじゃない」(大笑い)
そんなこと言ったことあるか?
(でも、でも。よく考えたら確かに身近に史上最強の女(ひと)がいる!もうこれ以上は勘弁して下さい。心の声)
「 ♪ いち、に、さん、し、アルソック!・・・」
アイディアで変わる!日本の収穫
2015.11.04
カテゴリ : 仕事/ビジネス/study
2015年11月3日(火)放送のNHKニュース、
おはよう日本のまちかど情報室で、またもや
『野菜・園芸用 ワンタッチ支え止め具』が紹介されました!
>
アイディアで変わる!日本の収穫。
植物が大きくなると支えが必要です。
支柱に植物を留めるのにひもを結ぶのが大変です。そこで、ステンレスのフック。
弾力性があるステンレスでできていて引っかけるだけで簡単です。
>
さすが。NHKさん太っ腹!
ありがとうございます。
言葉にできない
2015.11.01
カテゴリ : こども/カミさん/ファミリー
ある日の話。
「あ、今日はあの店ポイント5倍だ。行ってくるか」(私)
『じゃあ、ついでに頼みたいものがあるの』(カミさん)
「何?どんなもの」
『う~ん。。。。。。。言葉にならない』
「お前は小田和正か!」
ラ、ラ、ラ、ララ、ラ~ ♪
たくさんあったみたい。
子供の頃にはなかったもの
2015.10.31
カテゴリ : ローカル/占い/天気/現象
ハロウィン(Halloween)
そりゃもう街は大騒ぎさ!
トリックオアトリート!(Trick or Treat !)
ハッピーハロウィン!!(Happy Halloween!!)
ヒーユアー!(Here you are!)
せめて合言葉くらい覚えようかね