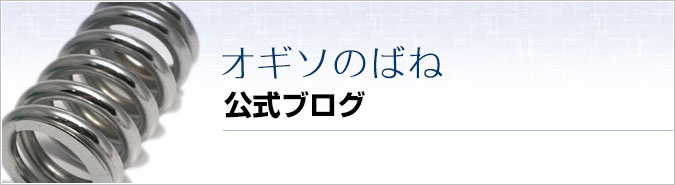
進化はしないが、変化はできる。できる男になってやる。
アキトの履歴書 60
2015.10.28
カテゴリ : ルーツ/アキトの履歴書
(祇園の一番花 あばれみこし 2)
伝統ある神輿も、その運行コースはあらかじめ決まっていて、
毎年、氏子から地元の宮田駐在所、駒ヶ根警察署に通行止めの許可申請をしている。
この日ばかりは、村中のみならず近隣近郊、遠方からも親戚・知人が祭り客として集まり、大変な人出となる。
村の決して広いとは言えない本通りの両側には全く空きがないほど露店が立ち並び、
その隙間を縫うように見物客が行き交う。歩くにも人、人、人で、通りはその熱気でムンムン状態となるのだ。
宮田のあばれみこしは県下に轟いていたので、その警備は厳重扱いされ、村の駐在さん一人ではとても立ち回れないと、
県警の機動隊員4人ほどが臨時に派遣されて、神輿の警備に張り付くのが“ならわし”だった。
私が、青年会の副会長そして会長だった過去2回、自宅前まで神輿を招き入れ、
皆に酒、水、御祝儀を用意し振る舞ったことは今でも自慢の種だ。当時の私に統率力がなければ不可能だっただろう。
しかし、最初に自宅前まで神輿を招いたときは、警備の警官らに
“運行のコースではない”と、即座にクレームがつけられた。
「私は役員であるし、我が家は宮田駅の目と鼻の先にあり、駅前の一部であるので文句は無かろう」
との、ずいぶん強引な話で正当化したのだが。
『火事と喧嘩は江戸の花』と云われるのと同様、
宮田の神輿(=あばれみこし)も威勢のいい時代であったかもしれない。あの頃の男子会員の中には、
“神輿は怖いから担げない”
という人が大勢居た。私は、
“万一、神輿の統率を乱す奴がいたら、つまみ出してくれ”
と仲間に頼み、実際のところ、本当にうまく進行することが出来た。
あの時の仲間・友達への感謝の気持ちは忘れない。持つべきは本物の良い仲間、友達であると痛感している。
アキトの履歴書 59
2015.10.27
カテゴリ : ルーツ/アキトの履歴書
(祇園の一番花 あばれみこし)
神輿の出発は夜7:00頃からだが、その前座としての祇園囃しの運行も大変重要である。神輿が出る前に、
町(通り)を浄める意味もある祇園囃しの運行を無事終える(夕方4:00頃)と、本番の神輿の出番が待っている。
私を含む会員(男子のみ)は、それぞれ一旦家に帰り、今度は急ぎ夕食をすませ、パンツにサラシ、地下足袋の姿で
津島神社に駆けつける。その後は、神事が終わるのを今度は担ぎ手として待つのだ。
私はこの年、青年会長であったので、神男としての役目を担っていた。
神輿に神を乗り移して町内を練り歩くという一大イベントの主役だ。夕方6:00頃、神社の社殿に馳せ参じると、
社殿の中は神主、氏子総代、商工会長、他の面々。神事に参列する方々で満員状態だった。
初めての私は恐る恐る入っていったが、神主さんから、「こちらへ」と案内があり、席に着いた。厳かの内に神事は進み、
玉串奉納となった時、神主さんから再び声がかかった。氏子総代の方から
『さあ、今日の主役は会長さん』(あんただから一番先に神様の前に行って下さい)
と言われた。私は、神主さんが行った動作を見よう見まねで玉串奉納したのだった。この時は内心
“神男って、えらい、すごい、カッコいい”
としみじみ味わっていた。
神事も済み、いよいよ今宵今晩、神を神輿に乗り移す儀式となる。神主さんが取り出してきたご神体を、
私も手伝う形で神輿の簾(すだれ)を開け、神輿の中へと招き入れ、その心棒に麻ひもをしっかりと結びつけた。
担ぎ手衆にお神酒が振る舞われたところで、私の、神男としての挨拶。
「祇園祭の一番花である神輿の出発に先立ち、一言ご挨拶申し上げます。本日ここに津島神社祭典が行われますことは
氏子総代様はじめ、関係各位のご尽力の賜物と心より御礼申し上げます。本日の進行は、神社を出まして南へ向かい
里宮にて折り返し、北へ向かい大曲がりを経てキネヤさん宅に出て本通りを元に戻り駅前に行き、折り返し
神社に戻って参ります。無事に帰ってこられますよう皆様のご協力をお願い申し上げます。以上。」
まさに祇園祭で一番の男の花道といえる瞬間。
一生一度の神男のこの挨拶口上も、伝統ある口上で代々引き継がれ、前会長から新会長へと口伝えされてきたものだ。
アキトの履歴書 58
2015.10.26
カテゴリ : ルーツ/アキトの履歴書
(祇園祭:ひき子復活で大盛況)
私たちの努力が天に通じたのか、祭り当日は、実に8年ぶりのひき子復活を祝福するかのような快晴となった。
朝早くから、幟(のぼり)立て、市松飾りつけ、神殿前の対の大きな龍燈設置、
山車の杉枝の飾り準備と人形の設置準備(人形師が高遠から出向いてきての飾りつけ)
男子総出で10時頃まで手分けしての作業は、大変な忙しさであった。
子供ひき子衆の参加者は、前日までに有線で放送して公民館に来てもらい花笠を渡した。久しぶりの復活だったが、
親子連れで大勢の方が取りに来てくれ、用意したものが足りなくなった。不足分は会員の分で追加補充した。
急ぎ家へ帰り、朝食をすませると浴衣と地下足袋、三尺(空色)、笛を風呂敷に包み津島神社へ行く。
(このパターンを毎年繰り返していた)
夜警所で囃し連の面々がそれぞれ浴衣にたすき掛け、越後獅子よろしくタツケをはき、足袋に草履履き。
頭に豆絞り、背中に花笠をつけて、芸人姿の完成である。
支度の済んだ者から出発場所である駒ヶ原の里宮(さとみや)神社へ集合。12時からの出発の為、大忙しで歩いていく。
その前に、先輩に運転をお願いしてある山車の荷台には大道具等を載せ、駒ヶ原まで運んでもらう。
里宮には、すでにひき子の親子連れを始め、女子会員、氏子の他多数が境内から溢れていた。
山車の準備と引手の綱の形を整えて、会長の私と氏子総代が短い挨拶をし、北を目指していよいよ出発である。
最初の越後獅子の演奏は、私にとって色んな意味で感動ものだった。
久しぶりのひき子連だったので事故がない様に前後注意をしながら、あらかじめ停車場所を設定してあるところまで
山車を運行しては、その都度、手踊り・囃子を行い、ご祝儀の披露をして進んでいった。
(当時、祝儀の披露は200円の場合それを10倍して、○○様ひとつ金2,000円也と言う)
当時は、300円位が多かった中で、タカノさんが破格の5,000円にはびっくりした。
(また、この年から数年後、タカノ商工会長さんのご尽力により、運行する専用の屋台が商工会より寄贈された。
今日に至るもなお、その本体は使用されている。それから、祭りの補助金も氏子に毎年出して下さった。
現在は、耕地で祭典委員を任命し、山車運行と神輿運行が行われている。)
この年の祇園囃し連には、見物客がとても多く、行く先々は大変な拍手喝采、大いに盛り上がった。
北町のはずれ(キネヤ)で大休止となったが、私は嬉しくて嬉しくて大感激だった。
駅前で休憩となり、ひき子全員へ参加御礼のお菓子を配布した。駅前の折り返しから神社までは帰り囃しである。
私は嬉しさのあまり、ヒョットコの面を借り、駅前から銭屋さん前に至るまでの道程でバカ踊りをした。
大成功と大感激で夢中で踊った。この時は人知れず、ヒョットコのお面の内はうれし涙と汗でびっしょりだった。
あの時の感動は今でも忘れられない。
町青年会長として会員の皆に資質向上や、その目的を理解してもらい一致団結したこと、何をどう遣り繰りすれば良いか、
私は大変ながら良い体験をさせてもらった。何より、大きな事業をやり遂げたという達成感を味わうことが出来た。
ご協力頂いた全ての方、事に、感謝の念を抱いた。
500年の伝統ある祇園祭り、年に一度のイベントで主役として果たせたことは、やれば出来るという自信になり、
私の人生の大きな糧となったのである。
くまモン。モノホンはいないモン
2015.10.24
カテゴリ : 閑話休題
九州には熊(クマ)がいないという事実。
あれから30年
2015.10.22
カテゴリ : 映画/本/エンターテイメント
“若い頃はよく愚痴をこぼしていました
あれから40年
今はご飯をこぼすようになりました” (by 綾小路 きみまろ)
いやいや。そうでなくて。
昨日、娘からのLINEに
『今日は、バック・トゥ・ザ・フューチャー(Back to the Future)の日だよ』って。
あー!ホンマや。あれから30年(1985年の映画公開から)もう経った!
来たよ。自分も。Back to the Future!
正確には、『バック・トゥ・ザ・フューチャー2』でタイムトリップした先(未来)が
2015年10月21日だったかあ。
あの頃は、もっと先(未来)と思ってたのにね。
今宵は、なつかシネマでもレンタルしてみようか?